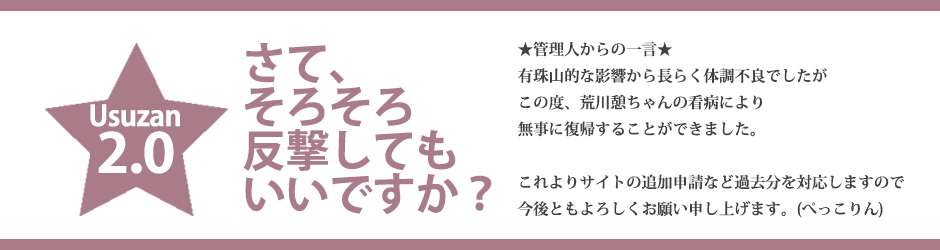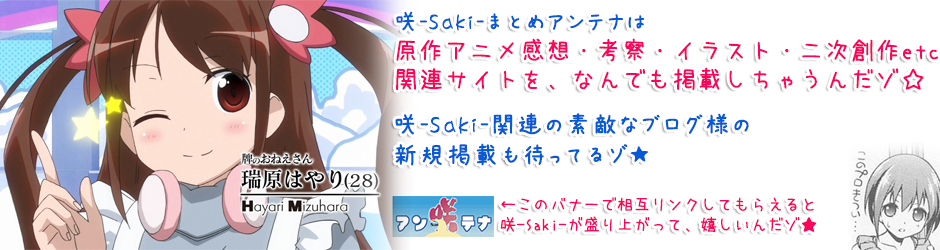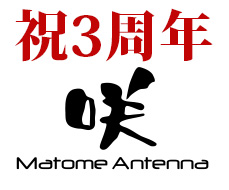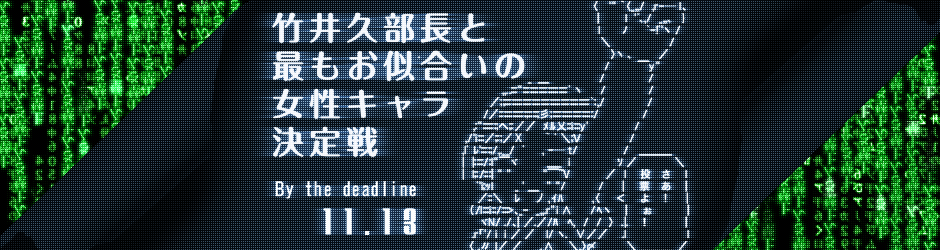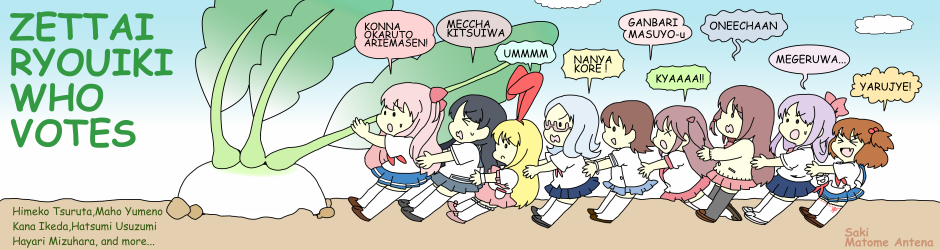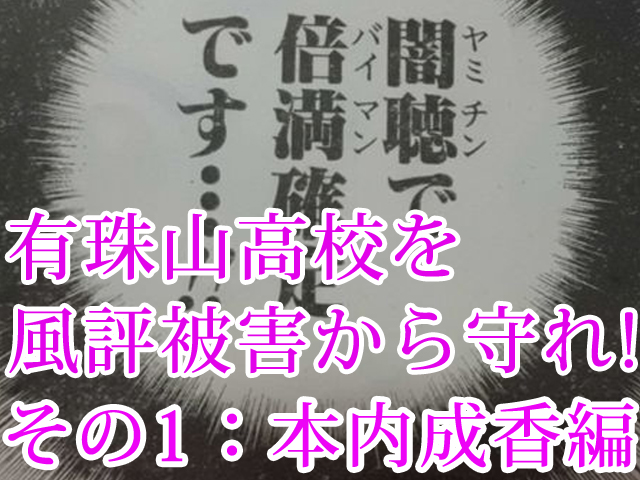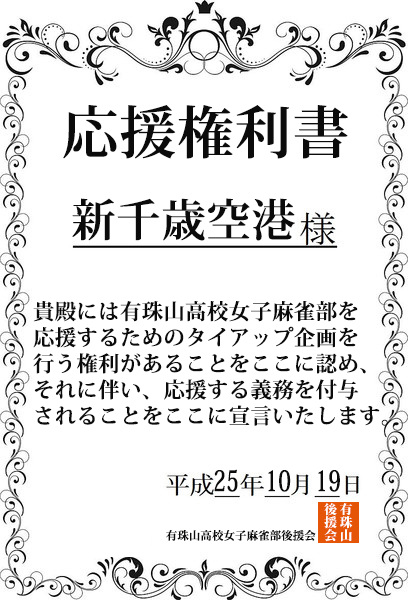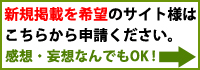十二月半ば
咲「もうすぐ十時になるのに、優希ちゃんも染谷部長もこないね」
部室の片隅、元いたベッドは反対の壁へ押しやられ、薄茶色で時代錯誤な円卓のコタツが置かれていた。
京太郎「部長も昨日は『絶対顔出すから!』なんて夜中の十二時にメール送ってきたのに、」
咲「え? 京ちゃんそんな時間に起きてるの? というか竹井先輩とそんな時間にメールしてるの!?」
須賀京太郎の対に座り、今のいままで本から視線を外さなかった宮永咲が驚きの色を隠さず、京太郎の鼻先に顔を近づけた。腕に顎を乗せ、だらけきった京太郎はたじろぐことすらできなかった。
京太郎「お、おう。部ちょ――竹井先輩も話し相手がほしいんだって。男友達が俺しかいなくてそれでいろいろ相談を……て、咲さん?」
咲「ふーん。そうなんだー。ほー」
京太郎にとって、ここまで不満を顔に出す咲は珍しかった。どこか感情の起伏に喜怒哀楽の怒がぬけているし、そもそも面と向かってしゃべるという事がここ最近少なかった。
自分のいないところでは――例えば原村和や片岡優希とおしゃべりをしているとき、勝手な想像だが、咲は憤慨などしないだろう。彼女らは人をおちょくったりしない。適度な暴走で咲を困らせるだけだ。
京太郎「なんだよお姫様。もしかして嫉妬?」
咲「!!、違っ――違うもん」